歌舞伎ソードが人気の時代に茨城にある甘デジ専門店に衝撃を受けました。
どこも5号機ショックに道を探し、アイムジャグラーEXが中古価格で100万以上の値を付けた時代に、甘デジの専門店ということで、中古機の使い方にそのヒントを教わりました。
新台の予算がもらえない現状に、それらのヒントを持ち帰り、1円パチンコの導入を地域一番で決断しました。
年間2~3機種ほどだった新台の海物語が、年間5~6機種の販売に増える中、全て中古の海。ほぼ甘デジをメインに、1円を構成し、4円コーナーには比較的新しい機械を残しました。
一物一価も厳しくなかったので、1円コーナーのみ0.6円交換でヘソは13.0まで開けました。
今では多々問題がありますが、これが、一番バランスの良かった時代と感じます。
お客様は勝ち負けだけではなく、遊べる、回る、ストレスがないことを重視し、毎日のように足を運んでくれました。
時に少し余力がある時に比較的新しく、まだ打ったことがない4円パチンコを少し打つ風景もあり、それはそれで、楽しんでいる様子でした。
財務的にも0.6円交換であり、機種は全て予算内の中古なので、取りすぎることもなく赤字になることも少なかったです。
しかし、長くは続きませんでした。
近隣の大手が1円パチンコを始め、それを等価で営業してきたのです。
新台の予算すらない当店と違い、大手はすぐに1円に新台を導入!という先制攻撃を掛けられました。
桁違いの広告費で大手の噂はすぐに広まりました。
当店もギリギリの闘いを強いられましたが、あくまで1円は中古で回す。利益を取りすぎないことを重点に、手前味噌ながら一部のお客様を維持した時期もありました。
しかし、それも2店舗間の闘いだからまだ出来たこと。そこへ3店舗目の大手が参入しました。
最終的には頑なに4円営業を守ってきた地域一番店までもが参入したことで、状況は一変しました。
一物一価の問題も浮上しました。
1円交換の場合、玉数×1円というわかりやすさが重要という市場調査から、当店も今では1.25円パチンコにて、1円交換の営業へと変わってしまいました。
当然、釘シートの問題もあるため当時の勢いはありません。
上記にある通り、1円を打つお客様でも少しの余力があれば、新台を打ってみたいのだと思います。
それが、1円で打てるとなれば、誰もが興味を持ち、お客様は流れてしまいます。
しかし、等価の1円では、回らない、出ない、ストレスを感じる、長くは遊技できない。
それらの客を離すまいと、貯玉や相次ぐ新台導入、囲い込み戦略を20スロが生きてるうちに大手は行います。
ご存知の通り、4円の顧客は離れ、唯一、高射幸性機種の残る20スロにて利益を確保し、1円を維持してきます。
そこに5スロに手を出すと、もはや、2番目に参入した大手ですら撤退する始末です。
結果、全国の遊技人口は減り、今に至ります。
もちろん、チャンスはありましたが、自分の力不足を感じています。
大手や誰かのせいではなく、稼働や利益や数値と闘うべき自分の無力や我慢が足りなかった、と。
今もなお、根底は変えずに営業努力は進めておりますが…。
変な話、40万する商品を1円ユーザーに打って頂くことは、勝ち負けの前にネタと売値が見合っていない。
寿司チェーン店が閉店するように、値上がりするネタに対して100円のお皿では、営業が成り立たないのではないかと思います。
それをわかっていながら、高級ステーキをg1円で提供する、してしまったことが、バランスの崩壊へと進んだのではないかと思います。
高い商品は、高い価格で売る。それが、普通ではないのでしょうか。
それが、高くても新しいから買うが、営業努力じゃないでしょうか。
甘んじてきた結果、今があります。
どんな、店長でも1円で等価で新台ならお客様は付けられるハズです。
それすら、できなくなった今だからこそ、危機感を感じて共に考えたいのです。
マーケティングで言えば商品は遊技機。価格は交換率。人によって価格は出玉、と見る方もいるのかと思います。
批判コメントの中の多くは、自身が出ない、負けた、つまらないが、根底にあるのかと思います。
「出ない」は、等価を止めて、新台を控えめにし、予算を削れば、出率は上げられます。
「負けた」は、10万勝ちたいのであれば、等価で一か八かもありですが、大勝ちを求めず負けを減らす。減らさせることは可能です。
「つまらない」は、遊技機自体を言われれば、モノづくり側の問題ですが、当たらないまま終わるや当たる確率を増やすことも可能です。
その全てに等価、新台購入、貸玉を下げるが、ネックにあることは、全国の店長さんも分かっている事実のハズです。
厳密にはみなし機や設置比率の問題など、それ以外の要因もあることも承知しています。だけど、隣がやるから…。
心理的に人は安く、新しいものにまず興味を持ちます。
いっそ、一部の地域は「16割分岐しか認めない!」とする。新台は年間何機種しか認めない!とか。
それを強みと考えた時に全国唯一の特化区域を創造する。
これは増えすぎたこの業界の20年先の話ですかね…。
少し批判的になりましたが、共に考えたいのです。
ダイナムパークさんの例があるように、今の状況は健全ですか? 異常ですか?
1台20万だった新台が、今40万なら貸玉は倍の8円であることが普通じゃないでしょうか!
4円等価で勝負できないなら、1円等価で勝負できるわけがないですよね。でも、隣がそれをするから、と。
メーカーはさておき、パチンコ屋がお客様の利、とならないことを気づいているのに、前に進まない、変わらない。
どうせ、無理だと言われるのもしょうがないと思います。
批判コメントに感謝です。
利とならないことを続ける意味はあるのでしょうか?
今こそ、気付くべきだと思います!
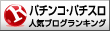 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。