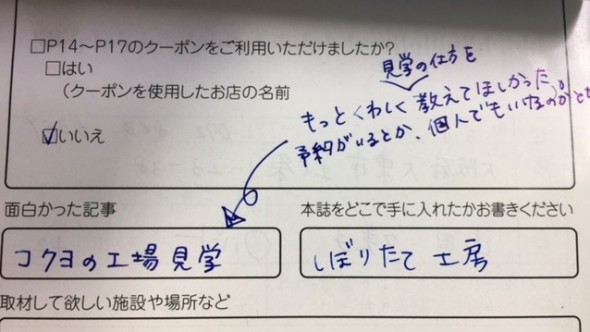出過ぎでビビる店長と、
出過ぎで喜ぶオーナーの温度差。
全国に点在するホール企業のDNAは、オーナーの性格が反映されています。
昔から一発台や3回権利モノが得意なホールチェーンが全国各地で頑張っています。
そんなホールのオーナー自身は確たるものとして、パチンコとは何かと言う持論を持っています。そんなオーナーの方針がホール企業のDNAとして何十年も脈々と続く。
一発台も3回権利モノも、設置する基本は、釘技術がしっかりあり、傾斜角度も丁寧に調整出来るかです。
でも、これらの調整をしっかりやっても失敗することはあるものです。
失敗とは、出過ぎと出なさ過ぎ。
そして出来るオーナーは、出過ぎでは怒らず次回へ繋げと檄を飛ばし、出ないと激怒するのです。
それくらいの覚悟がないと、ライジンマンや今日もカツ丼を導入してはなりません。
パチンコの本来の楽しさは、まったりと玉を追う。
これなんですね。
言うなれば、ピタゴラスイッチ的な感覚。
まったりと玉を打てて、万が一Vに玉が入る瞬間があれば熱くなれる。
これがアナログパチンコの良さ。
ずっとハラハラでは疲れてやがて打つのも嫌に。
初代ゼロタイガーのスペックを覚えている業界人は少なくなりましたね。
当時は無制限(ノーパンク)制なんてなくて定量制。
3000発や4000発打ち止め制が大半でした。
そして初代ゼロタイガーは、Vに1回入ったら、羽が可動を始め、その間にVにまた入ればまた次の羽の可動カウントがスタートするから、
運が良いと一気に打ち止めになります。
200円分の玉でVに入ったとすると、一気に打ち止め終了! そんなことが結構ありました。
その後、ゼロタイガーは、ラウンド数と羽開閉数の固定により、一気打ち止めになる事はなくなりました。
当時は、三鷹駅前にあった○○○○○○本店に初代ゼロタイガーが設置されており、電車で通うファンが朝から並んでいたものです。
あの時代の本店の店長は、出過ぎる初代ゼロタイガーに手を焼きましたが、後に自身の店の看板台に育てました。
初代エキサイトジャックを覚えている方もいますよね。
これに手を焼いたホールも結構ありました。
当時20店舗あった北関東のあるホール企業は、12店舗で初代エキサイトジャックを導入しました。
これが連日赤字。
初代エキサイトジャックの特性として、大連チャンする時がありました。
4連チャンは当たり前、波に乗ればそれ以上も連チャンする。だから朝から満席になるくらいお客さんが来店。
店長会議では、初代エキサイトジャックの対応が議題に上がりました。
スタートまたはTYを下げるか議論になった時に、営業担当の常務は、「薄利多売で行こう! 目標割は14.3割。極力スタートは下げずTYで調整」と方針を打ち出しました。
稼働がある間は、お客さんに遊んでもらいましょう!トータルで粗利が取れたら良いと。
これらの例は、最初は利益が取れなかった機種だが、やがて看板台になった例。
初代エキサイトジャックの連チャンは、当時の麻雀物語よりも破壊的でしたね。
真相は闇の中ですが、初代麻雀物語の初期出荷分の連チャン率は25%。2期出荷分は20%だとメーカー系の営業マンから聞きました。
確かにそれはデータにも現れて、私の担当したホールは2期出荷分の麻雀物語でしたが、同じチェーンの初期出荷分の麻雀物語の方が連チャンしてました。
話を戻すと、あの当時、40玉交換が主流でした。
損益分岐点は16割。
基本の割数は12.5割から13.6割の時代に初代エキサイトジャックは、連日16割の出玉ですから、出玉感はハンパないわけです。
この時に、他の機種とのスタート数との兼ね合いを見ながらスタートを5.6くらいにしたのですが、これを一気に下げると回らない機種との印象が残るから調整方針が重要でした。
つまり、お客さんと店とのせめぎ合い。
それと、店と遊技機とのせめぎ合いの毎日でした。
昔のオーナー達は、せめぎ合いこそがホール運営の楽しさと受け止めていたから、、なんとかして、機械を活かそう活かそうとしていたんですね。
現在はどうでしょうか?
出過ぎにビビり、最初から閉め閉めの調整をしたり、
出過ぎにビビり、稼働を打ち切るケースが散見されます。
これでは、何も生まれません。
じゃじゃ馬機種を上手く操る前に放棄しないで、
じゃじゃ馬を乗りこなす調整を身につけるチャンスと捉えて、ライジンマンや今日もカツ丼を稼働させたら良いのに、と思います。
あるチェーンが、70歳台後半の釘師を講師として招聘したことがあります。
スーパービンゴやラプソディの時代に活躍した元正社員の店長兼釘第一人者の釘師は、昔の釘技術を伝承させる為に、オーナーが呼び戻したのです。
これから先、パチンコから釘が無くなるかも知れない時代に、なぜ今また?と思う人もいるでしょう。
理由は、今の店長や釘担当者の釘技術低下に危機感を抱いたからです。このままではあと10年すると、本当に釘技術の伝承者がいなくなると思いました。
そして、いつかまた、羽根モノや権利モノの類で良い台が出た時に、釘が重要になってくると期待しているのです。
メンテナンスのための釘調整でも、やはり技術がないとじゃじゃ馬を乗りこなせない。
暴れん坊でもじゃじゃ馬でも、投げ出さずに、根気よく考えて、機械を活かす。これを思い出して頂きたいですね。
投げ出さずのは簡単ですから。
つづく
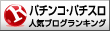 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。