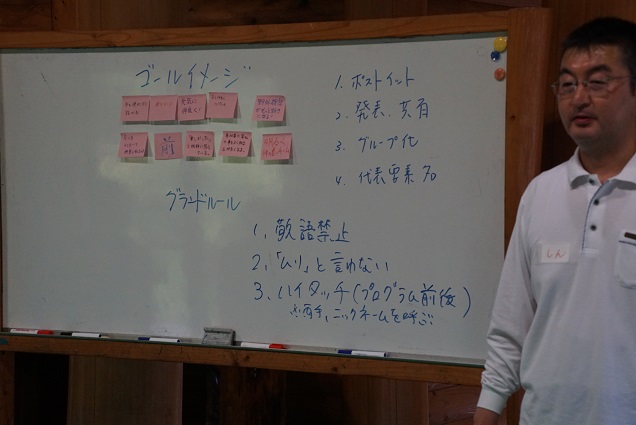法案の目的である第一条は次のように記されている。
第一条 この法律は、ギャンブル等依存症がこれを有する者等及びその家族の日常生活及び社会生活に様々な問題を生じさせるおそれのある疾患であり、ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下同じ。)及びギャンブル等依存症を有する者に対する良質かつ適切な医療の提供等によるその回復等が社会的な取組として図られることが必要であることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル等依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健康を保持するとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
法案提出を終え、IR推進派の自民党・岩屋毅議員は自身のFacebookで「パチンコ、公営競技、麻雀などで多重債務や自閉症家庭暴力で苦しんでおられる患者の自立 、更正、 予防を図るため、 全力を挙げてまいります」と抱負を述べている。
法案成立後は国も交えて依存症問題に取り組むことになる。
ギャンブル依存症対策法案はパチンコ業界とて例外ではないわけだが、自民党関係者がこう打ち明ける。
「今後ギャンブル依存症を増やさないためには、まず、パチンコ依存症を増やさないように規制することになる。ただ、現状ではすでにサラ金規制で借金してまでする主婦は減っているし、出玉規制も実施されたので、スタート時点ではこれ以上規制を受けることはない」と前置きした上で、こう予測する。
「依存症が増えた場合は、確変やオマケ100回が禁止され、今よりももっと出玉が抑えられる可能性がある。日遊協の会長が遊技人口を2000万人に復活させると発言しているようだが、そんなことしたら大変なことになる。依存症が増えるに決まっている。そんな発言は、今はヤバイよ」
パチンコ業界は依存症を増やさずに、遊技人口を増やすという超難題に立ち向かわなければならない。
ところで、ギャンブルの中でもあまり依存症問題が関係ないと思われているのか、宝くじがテレビCM攻勢をかけている。数字選択式の「ロト・ナンバーズ」は稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾を新CMキャラクターに登用して初心者を囲い込む作戦に出ている。

書店のギャンブルコーナーからはパチンコ関連本が姿を消し、ロト・ナンバーズ関連の攻略本が棚を占めている。実に世相を反映している。
当然、宝くじ依存症の人もいるわけだが、まだ数が少ないのでパチンコほど問題にならない。
ギャンブル依存症対策基本法案の基本理念には次のように記されている。
ギャンブル等依存症の予防等及びその回復を図るための対策を適切に実施するとともに、ギャンブル等依存症を有し、又は有していた者及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
支援するのはいいが、その財源はどこから?
先の自民党関係者はこう話す。
「ギャンブル依存症の大半はパチンコなので、9割ぐらいはパチンコ業界からから出させたらいいという意見が有識者の間であることも事実です」
これが民営ミニギャンブルの負い目でもある。
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。