直近の4月25日放送分の「そこに本人や家族の声はあるのか~ギャンブル依存症対策~」では、ギャンブル依存症対策基本法案の中身を巡り、当事者や家族、行政や医療者、民間団体の支援者の他、業界からは全日遊連の副理事長や匿名のホール社員がインタビューに答えた。
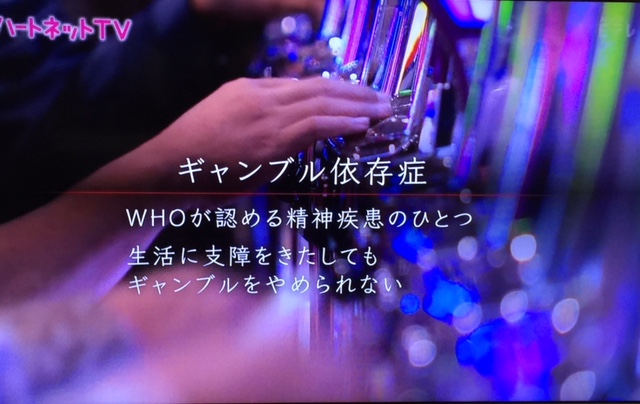
さて、政府が発表したギャンブル依存症対策の中身に対しては、ギャンブル依存症の回復施設の関係者から見たらこんな具合だ。
「予防対策として、現時点でパチンコやギャンブルをやったことのない人には入口の対策としてはいいかも知れないが、現在ギャンブル依存症で回復が必要な人には分かりづらい」とばっさり切り捨てられた。
ギャンブル依存症でも一番割合が多い、とされるパチンコ業界の依存症対策に全日遊連の幹部が答えた。
「各ホールで依存傾向にありがちな人に適切なアドバイスができる人材を育てようということでパチンコ・パチスロ安心安全アドバイザー制度を作った。1日の研修で認定を受けられる」と業界の新たな取り組みを紹介すると共に、以前から進めているリカバリーサポートの相談窓口について語った。
その後、依存症=幽霊説の持論を展開。放送を見たギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表から大顰蹙を買うと共に、「たった1日の研修でアドバイザーは育成できない」と自身のブログで批判されてしまう。
では、現場のホールスタッフは依存症対策をどのように捉えているのか? 匿名でホール社員がインタビューに答えた。
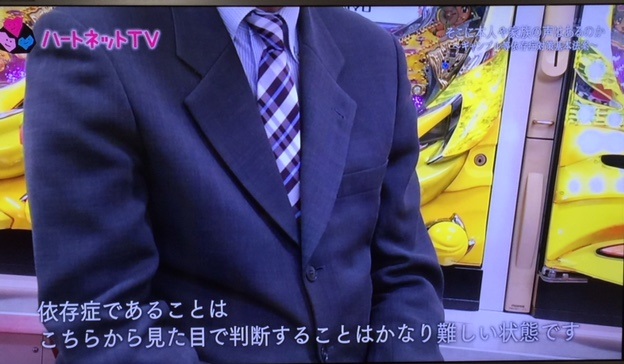
「依存症であることを見た目で判断することはかなり難しい。かなりおカネを使っているお客様へお声掛けした場合『うるせ!』と怒鳴られてしまう。1人ひとりの投資金額を全員見張っているわけではないので難しいところがある」とアドバイザー制度に懐疑的だった。
さらにこう続ける。
「リカバリーサポートネットワークに1人で悩まずに電話で相談ください、ということはやはり自己申告して下さい、ということになる。ご自身で分かっていればこういう問題は起きないが、ほぼ全員自覚がない状態。依存症対策はIRがきっかけで話題になっているけど、そもそも業界がやるべきことをやっていなかったことは確か。パチンコは自己責任で適度に遊ぶものと、業界は現実逃避して自己責任に押し付けていたのでは」と自身の見解を述べた。
パチンコ業界が依存症問題に取り組んでこなかった、というのはちょっと間違っている。
業界では18年前の2000年頃、真っ先に依存症問題に取り組んだ先駆者が大分セントラルの力武社長で、2002年4月には全日遊連でも「パチンコ依存症研究会」を立ち上げている。そこからリカバリーサポートへとつながって行く。
研究会が立ち上がった当初は「なんでそういうデメリットになるような問題に積極的に関わるんだ」との反対意見が多かったことも確かだ。パチンコ業界は、マニアを作るのが仕事であって、それを依存症呼ばわりして排除したら産業自体が冷え切ってしまうのではないかとの危惧があった。
ここに業界に本音が集約されている。
マニアを増やせば依存症も増える。このジレンマと業界は戦い続けてきた結果が今である。
依存症に取り組む久里浜医療センターの樋口医師によれば、ギャンブル依存症の人は「重複障害」を持っている人が多い、という。精神的問題や対人関係があったりした場合は、単純にギャンブルを止めればいい、という問題ではないらしい。
回復施設の施設長は自らもギャンブル依存症だった。子供の頃から親に虐待され、抑圧され続け歪んだ青少年期を過ごした。ギャンブルを始めたらそこに自分の居場所があった。
パチンコ・パチスロで500万円の借金を負った23歳の大学生は、最後の1カ月間はおカネに困り、盗みや万引きを繰り返しパチンコと酒に溺れた。
この大学生は言う。
「中学高校で友達から酒タバコを覚えさせられた。ギャンブルを始めて人生が狂ったのではなく、ずっと狂っていた人生がギャンブルで表に出ただけ」
このように背景にある問題を含めて、原因を見つめ直す総合的な対応が必要になる。ギャンブル依存症が心の病気と言われる所以である。
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。