パチンコ業界版船中八策を打ち出して、業界の未来図を描くことのできるリーダーはいないのだろうか?
全日遊連の理事長の中には、未だに原田派と山田派とに分かれている、という。警察受けのいい現執行部か、行政にもものがいえる改革派か、といったところだろうか。これだけでも目に見えない対立構造がある。
現実は業界人の誰もがギャンブル産業だと思っているのに、建前は警察行政を含めて大衆娯楽、といい続けているところにそもそもの無理がある。こうした基本問題から解決していかないと業界の未来は開けない。
業界に入った時からすでにギャンブルと化していたパチンコ業界しか知らない世代が、2代目経営者となっている。その彼らは青年部として活躍しているが、親組合からすれば、子供のような存在でしかない。
親世代はこれまで換金問題を筆頭に警察行政のお手盛りで、グレーゾーンの中で生きてきた。グレーゾーンにドップリ浸かっていれば、それが楽で一番いい。しかし、子供の世代ではいつまでもグレーゾーンの中では生きてはいけない。子供はグレーゾーンから抜け出したいことを願っている。
最近のケースでいえば一物一価の問題がある。
この指導も全国一律ではなく、各県警によってかなりの温度差がある。県によっては二物二価が黙認されているケースだってある。
警察庁が一物一価を指導しているのなら、県警から厳しく指導されるまで、甘んじるのではなく、率先して一物一価を実施しよう、というのがグレーゾーンからの脱却を図りたい子供の考え方である。
ところが、親は長年グレーゾーンの中で生きてきた経験から、「警察から引き金を引かれるまで急ぐことはない。どうせ、組合の自主規制で早くやっても、守れないところがでてくるので、やる必要はない」と突っぱねる。
子供の意見は一喝するだけではなく、サンドバック状態で叩くだけ叩いて、組合会議で発言するのが嫌になるぐらい打ちのめす。
改革に燃える子供の中には、組合の取り決めは一切従わない、とグレる子だって出てくる。
業界がどんどん衰退していっている理由は、これまでと同じ間違ったことをやり続けているから他ならない。
改革とは挑戦することである。
全日遊連が何か新しいことに挑戦しただろうか?
その挑戦をするのが全国青年部の役目であるが、過日、名古屋で開かれた全国青年部の集いを取材した業界誌記者からは「ぬるさ」の中で終わった、との批判もあったようだ。
しかし、彼らの中にも改革に燃える経営者がいることも事実である。
全国青年部から業界版の船中八策が出ることを期待する。
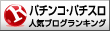 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。

