パチンコを衰退させている理由の一つに2011年10月から行政指導を受けた一物一価の徹底が挙げられる。それまではスロットは5枚交換の等価交換で、パチンコは30~35玉交換のいわゆる一物二価で営業していた。
全国の大半のホールがスロットは等価で営業していて、なおかつ、パチンコよりも稼働がいいために、スロットに合わせた一物一価を選択するしかなかった。一物一価の徹底で4円の客飛びに拍車をかけることになる。
「全日遊連が等価を止めようという発想がないのがダメ。等価釘がお客さんの負担になっている。お客さんはホールがぶっこ抜いているというが、それは違う。スロットの等価に合わせたからこうなった。全日遊連は一物二価を認めてもらう努力をやったのか!」と怒りをぶちまけるのは都内のホールオーナー。
日報でも一物二価を認めてもらうことを何度も提案してきた。このまま一物一価が徹底されたら、業界は破滅の道を辿る、と警鐘も鳴らしてきた。こうして、ホールオーナーからも一物二価の容認を求める声が挙がるということは、現場が困窮している表れでもある。そう考えると、一物一価の徹底は業界を縮小させるためのキャリア官僚の頭脳プレイでもある。釘調整や3店方式など、法律を徹底的に遵守させればパチンコ業界は消えてなくなる。
「パチンコとスロットはそもそも性能的に別物なのですから、それを一物一価で括ること自体がおかしい。組合は一物二価を認めてもらうための研究をしてもらいたい」(同)
一物二価ではないが、二物二価の考察をしているのが元船井総研の小森勇氏である。2012年10月25日付のエントリーを再掲する
いったい2物2価とは、どういった状態を指すのでしょうか? 今年7月のプレイグラフ誌に三堀清弁護士が論考されているのが大変参考になります。それによると、2008年7月3日の石川県警の文書が参考になるとの由。
それによれば「特定の遊技球等に対する賞品を(それぞれ)設けて、客の賞品選択の自由を排除するものであり、いずれも換金行為を前提とした賞品提供方法である。」と指摘されています。
これによれば、賞品として一般商品が提供される際には、敢えてPとSとで賞品を区別しないのに、“特殊景品”の場合だけPとSで提供賞品を分け、2種類用意することは、客の賞品選択の自由を排除することになる!更に結果として「賞品取りそろえ義務」(風適法施行規則35条2項2号)の主旨に反することになる。
また換金行為を前提とした提供方法である!というものであります。
この石川県警の見解に対し弁護士の三堀氏は、民法第586条(交換)の法理解釈上は、ぱちんこ店側にも賞品提供者としての営業の自由がある程度ある!という解釈も成り立つ、と指摘されています。
これは大変興味ある指摘です。
と言いますのも、民法は私的自由を最大限尊重する法体系を前提にしており、風適法もそうした私的契約自由の原則の“行き過ぎ”を規制する行政法ではありますが、いくら民法よりも行政法が優先するとは言っても、自ずと限界があるというのが、法曹界の通念だからです。
この見解でいくと、賞品交換のリクエストを受けるP店側にも、ある程度提供の自由の幅を持たせてよいのではないか?という見解も出てきます。
例えば私が考えますに、5スロを初導入するホールからすれば、当面5スロ客をバッチリ付けんがために、期間限定で5スロ限定のロールケーキや北海道内限定流通のポテトチップスを5スロ用にのみ提供する自由は認められると思います。
なにせ我が国は資本主義、自由主義経済の国ですから(笑)。
賞品取り揃えとは言っても、ぱちんこ店は物品販売業ではなく、あくまで交換業なのですから、20円スロット客が強引にその限定ロールケーキを欲しいと主張しても、お店側は「ごめんなさい、期間限定で5スロ用なんです」と言っても違法とは言えないのです。
三堀弁護士も仰る様に、お客の持っている権利と言うのは「賞品交換が可能という期待権(期待利益)」だと思うんです。
問題は、これを所謂「特殊賞品」にも当て嵌めることが可能か?という点です。
結論的に私見を述べますと、1つ屋根の下で1つの営業許可証の下で営業を許されているホールとしては、難しいのではないか?と考えます。やはり「特殊賞品」というものは今日の現実では流通価値の極めて弱い物品が使用されている点から見て、ホールは突っ張れないと思います。
これに対しては、次のような反論もありうるでしょう。
つまり、「ぱちんこ遊技機」と「回胴式遊技機」は型式試験の種類も違い、公安委員会によるホールへの販売許可も型式の違いを前提とするから、PとSの賞品を共通のものにしなくても良いのではないか?と。
私見/確かに形式的には型式がちがいますが、同一営業許可証のもと、同一屋根の下で営業を営む以上、賞品だけ別ですよ!というのは理屈的に通りにくいと考えます。
やはり、ここはP店とS店、あるいは4円P店と1円P店とは、別々の営業許可証を取得して、提供賞品を別々のものを提供すべきだと思います。
昨今、PとSのW店舗、ないし4円P店と低玉P店のW店舗の許可がなかなかもらえない!という声が聞こえてきます。
思いますに、前回と今回で考究させて頂いた議論をしっかりと県警ないし所轄と話し合われると、法理論的にはW店舗を認めないとする論拠は大幅に減ると思います。あえて言えば出入り口を別々のものとすることによる、消防法上の規制の関係とか、駐輪場の設置場所とか、そんな店を1個1個つぶしていくべきだと思います。
以上引用終わり。
4年前のエントリーなので多少状況が変わっている部分もあるが、風営法に詳しい三堀弁護士に一物二価や二物二価の可能性について相談してみるのも、一物一価からの脱却の一歩でもある。
その前に撤去問題もきっちり期限内に片づけないと警察庁に聞く耳を持ってもらえない。
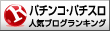 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
