2016年現在、パチンコ市場は大きく変わろうとしている。
と、その前にパチンコ業界の歴史を振り返ってみる。
1920年 ヨーロッパから輸入されたコリンゲームが大阪で登場し、これがパチンコの原型となった。
1930年 名古屋において初めて風俗営業1号店として営業が開始された。
1937年 支那事変悪化から、戦時特例法として禁止となる。
1946年 戦後パチンコ営業は再開される。
1948年 正村竹一により現在にも繋がる画期的ゲージ(正村ゲージ)が発明される。
1952年 連発式登場
1954年 連発式禁止
1960年 チューリップ登場
1972年 電動ハンドル導入に100発/分規制となる。
1977年 スロットマシン登場
1978年 「インベーダブーム」によりパチンコ衰退
1980年 三共「フィーバー」登場
1981年 平和「ゼロタイガー」登場
同年 30秒10ラウンド規制
1984年 15秒10ラウンド規制
1985年 新風営法(風営適正化法)施行、パチスロ1号機登場
1988年 パチスロ2号機登場
1990年 16ラウンドに規制緩和 ※釘曲げしないことの条件付き
同年 パチスロ3号機登場
1992年 パチスロ4号機登場
1994年 空前のCRパチンコブーム到来
1996年 パチンコ「社会的不適合機」撤去、確変5回リミット開始、当たり確率1/360以下に
1999年 当たり確率1/320以下に
2002年 当たり確率1/360以下に、最低賞球5→4個に
2003年 空前の爆裂パチスロブーム(ストック機、AT機)
2004年 当たり確率1/500以下に、最低賞球4→3個に
2006年 当たり確率1/400以下に、パチスロ5号機登場
2007年 パチスロ4号機完全撤去に
2008年 1円パチンコ増加する
2009年 パチスロART爆裂機登場、現在のパチスロ撤去問題の基となる
2012年 最低賞球3→1
2015年 当たり確率1/320以下に
2016年 パチンコのベース(役物比率)問題で、パチンコ台の殆どが年内撤去となる
これまでのパチンコ業界は射幸性の高まりと、それに対する規制とが数年毎に行われてきた。しかしながら、今回のパチンコの撤去問題はこれまでとは本質的に異なっているようだ。
なぜなら、CR機が登場して20年以上全メーカーが騙して遊技機の認可となる「検定」を取得し続けたことが発覚したからだ。
要するにパチンコメーカーは規制に抵触しないようなクギ調整した台で「検定」を通し、認可を受けた後に検定と違う釘曲げをしてホールに販売し、ホールはホールで営業調整と称して、また釘曲げをするというものだ。
パチンコもパチスロも同じで、国家公安委員会が定める「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(以下、規則という)で大当たりで出た玉とそれ以外の入賞で出た玉との割合を示す「連続役物比率」として60%以下(役物が連続しないものは70%以下)と定められている。
いわゆるデジパチ(セブン機ともいう)は、フィーバーすると役物のアタッカーが連続することから、そのアタッカーに玉が入り配当される玉が連続役物で払い出された玉となる。
パチンコ営業者においては、これをホールコンピュータでいう「ベース値」にあたるものである。
連続役物の割合が60%以下ということは、逆にいうとホルコンで表す「ベース値」となり、すべての出玉中の一般入賞(大当たり以外の出玉)の割合が40%以上ということであり、 これが、公安委員会の「検定」を受けた正規のパチンコである。
ところが、実際はこのベース値が10%~20%程度で営業をしていた。
警察庁が昨年来調査を実施した結果、実際にホールで営業されているパチンコ台の殆どが認可したベース40%以上とは程遠い異なる遊技機で営業していることが判明した。 いわゆる「検定」を受けたものでなく違法機といえるものであった。
このベース削りはお客の消費金額を著しく増加させてしまうことから、悪質性が高い。
この問題は、4月27日の衆議院の内閣委員会でも取り上げられ、河野国家公安委員長が不正パチンコを業界団体で自主的に撤去させることを明言している。
ここで問題になってくるのは、ベース問題を解決するのは業界にとって当然のことだが、営業実態として大変な問題が出てくる。
ホールの売上げが激減することである。
仮に出玉がトントンで1時間6000の発射玉があり、セーフ(配当玉)も6000発として、そのうちベース20%にあたる1200発がお客に小当たりで配当すると4800発が飲み込まれたので、4800×4円=19200円の売上げがある。
これを正規台にして営業するとベース40%(2400発)とすると、6000-2400=3600発で14400円となる。
※1時間あたりの売上性能として、ベース20%と40%では4800円の大きな違いが出てくることとなる。
この売上の低下は何百台もパチンコを設置するホールにとっては大きな問題である。特に上場を目指す大手法人にとってはその痛手が大きいだろう。
冒頭のパチンコ歴史でも 規制 → 不況 → 新発明 → 好景気 → 規制 と繰り返してきた。
この玉単価(玉1個当たりの売上)の低下は、ベース問題が発覚した以上、違法な釘曲げなどして解決できるようなものではない。
パチンコには1分間に100発(400円)の発射玉制限があり、ベースが上昇してしまうと直接玉単価に影響する。
※約半分50発(200円)はお客に戻すような仕様になる。
この低下した単価を今のように維持したいのなら、定量性などを用いるなど、営業方法に新たな方式が必要になってくる。それと同時に現在のパチンコでは自ずと限界が感じられる。
ベース40を維持しながらなおかつ営業が成り立つ遊技機とは、温故知新の中に答えがある。
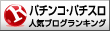 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。