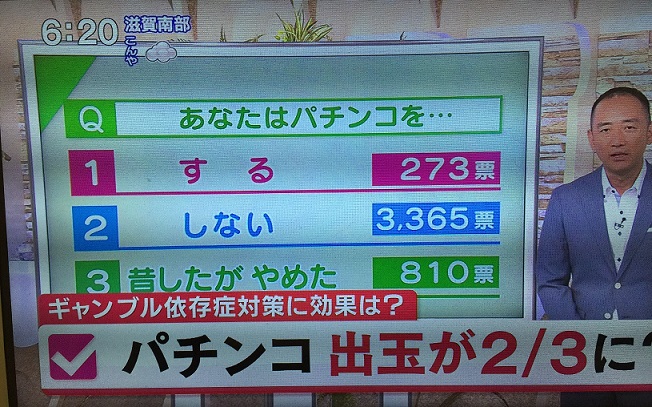決算書は1年間の通信簿といわれているが、高収益の源となっていた高射幸性機がパチンコ、スロットとも撤去され、新基準機の評価が減収減益決算につながった、と言っても過言ではない。
パチンコ産業は、かつては装置産業と言われていたが、今や規制産業の最右翼だ。遊技機の規則が変わるたびに、売り上げが大きく左右される業界もパチンコ業界を置いて他ない。
一連の規制はカジノがらみと今さら泣き言を言っても始まらない。業界が低射幸性時代に舵を切り、いかにして売り上げも上がらなければ、利益を確保することもできなくなった現在の機械で、どう乗り切るかを真剣に考えるターニングポイントになるのが2017年でもある。
ホールはメーカーばかりが儲かっている、と批判してきたが、メーカーも上位メーカー以外は全然儲かっていない。増収増益だった2社も今年後半から来年にかけて5.9号機が売れる要素もないので、来年はどうなるか全く分からない。
版権モノで鉄板のビッグコンテンツですら8万台売るのがやっと。パチンコの初代AKBが20万台売れた時代は数年で遠い過去になってしまった。
「仮に10万台は売れると踏んで部材発注をかけたとしましょう。ところが実際に2万5000台しか売れなかった場合は、7万5000台が在庫として残る。製造原価が50%とした場合、150億円が不良在庫として残る。中小メーカーなら一発で破たんします。原価割れして20万で売ろうとしても、『いらん』と断られるのがオチ。発注ミスをすると大損失につながります。だからビッグコンテンツでもそんなに発注をかけなくなった」(メーカー関係者)
北電子のジャグラーが売れるからと言って大量に販売しないのは、その辺の意味合いがあるからだ。
メーカーの販売計画が狂うと、開発予算にしわ寄せがいく。開発予算が削られると影響を喰らうのが下請けの開発会社だ。
パチンコもスロットも液晶が主流になり、映像関係は特に下請けを使うようになった。
「パチンコ業界は映像のノウハウがなかったので、下請けにお任せでしたが、相手の言い値で随分高い開発を払っていました。アニメ業界の下請けは年収200~300万円で働いているのに、パチンコ業界は下請けの映像制作でも年収1000万円は貰っていましたからね。それで人員を増やした会社が、大口のパチンコメーカーからの発注が止まったことで、倒産しました」(同)
業界で甘い汁を吸っていたところから、業界からの退場を余儀なくされている。
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。