「マーケティングの革新~未来戦略の新視点」の著者T.レビットによると「経営者の近視眼が悲劇を招く」と説いています。では、その著書よりパチンコ業界に関連することを参照していきたい、と思います。
重要産業といわれるものなら、皆、かつては成長産業でした。ところが成長産業の波に浮かれている産業の中に、衰退の色濃く宿したものがあります。成長の最盛期と考えられている産業が、実際には成長を止めてしまった場合があります。
いずれの場合でも、成長が怪しくなり、鈍化し、あるいは停止した理由は、市場が飽和したからではありません。
経営の失敗があったためだといえます。
“目的の取り違えが命取り”
失敗はトップの失敗なのです。つまり、失敗の責任を負うべきは、企業の広範な目的と政策の決定権者である「経営者」といえます。
[輸送産業]
鉄道産業が成長を停止したのは、旅客と貨物の輸送に対する需要が減ったためではありません。需要は増え続けています。
今日、鉄道会社が危機に見舞われているのは、旅客と貨物が他の手段(自動車、トラック、航空機、電話にまで)に奪われたためではなく、鉄道会社自身が、それらの需要を満たすことを放棄したからです。鉄道は自らを「輸送産業」と考えるのではなく、鉄道事業とし考えてしまったために、自分の顧客を他へ追いやってしまったのです。
なぜ、事業の定義を誤ってしまったかというと「輸送を目的と考えずに鉄道が目的」だと考えてしまったからなのです。すなわち、顧客中心でなく、物(鉄道という形)中心に考えたためです。
[娯楽産業]
ハリウッドは、テレビに徹底的にやっつけられることから、辛うじて救われています。現実には、すべての一流映画会社は、昔の面影を残さないほど大改造されてしまいました。なかには、早々と消滅したものもあります。
映画会社が例外なく危機に陥ったのは、テレビの侵入のためではなく、自らの戦略が近視眼なためです。
鉄道と同じく、ハリウッドも事業の定義を誤ってしまったのです。本当は「娯楽産業」なのに「映画産業」と考えてしまったのです。
「映画」という製品は、限られた特定の製品なのだと考えてしまうと、愚かな自己満足が生まれて、映画制作者は初めからテレビを脅威と見ていました。ハリウッドはテレビの台頭を自分たちにとっての好機~娯楽産業をさらに飛躍させてくれる好機~として、歓迎すべきだったときに、これを嘲笑し、拒否してしまったのです。
今日のテレビは狭く定義されていた昔の映画産業よりもはるかに大きい産業です。
ハリウッドが製品中心(映画をつくる)ではなく、顧客中心(娯楽を提供する)に考えたとしたら、あの惨めな財政的地獄から逃れることができたのではないでしょうか。
土壇場でハリウッドを救い、最近の再起をもたらせたものは、かつての体質の映画会社を打倒し、映画界の大物を動揺させながらテレビで名を上げた前歴を持つ、一群の若手ライター、プロデューサー、ディレクターたちだったいうのも考えさせられるところです。
一時は30兆円産業ともいわれたパチンコ産業が今は、非常に不安定な状態で、個々の店舗を見れば、方向性を見失い混迷しています。
いうまでもなく、パチンコは戦後の日本経済の復興と軌を同じくして、成長し続け、庶民の娯楽としてはNo1の地位を占めており、現在も十分な需要があります。
競争の激化や規制による機械の入れ替え、機械価格の高騰などの外部環境の変化が、需要の変化をもたらした、とは思えません。
パチンコ店に陰りを与えているのは、外的要因ではなく、需要を満たすことを怠った内的要因ともいえます。
パチンコ店は本来「娯楽産業」であるはずなのに、業界がギャンブル産業へと舵を切ったために、娯楽としてのパチンコを楽しみたい顧客を徐々に他へ追いやってしまった結果が、現在の疲弊したホール状況ともいえます。
T・レビットに倣えば、今のパチンコ業界はお客様中心(娯楽を提供する)ではなく、機械中心(ギャンブル性の高い機種の導入)に考えている、ということです。
鉄道会社や映画産業と同様に、パチンコ店も事業の定義を誤っている、といえます。
本来は娯楽産業なのにパチンコ機械産業と捉えてしまったのです。
今、業界に求められるのは事業の定義をパチンコ店の原点である「娯楽の提供」へ戻すことです。
さらに、店舗中心ではなく、「お客様を中心」に考えを切り替え、それを実行することがこの不透明で不安定な時代に勝ち残る条件といえます。
そのためには、地域の需要、情報を的確に掴み、お客様のニーズに適応した営業へと結びつける仕組み作りが大切になります。
また、機械は本来は手段であり、営業サイドが甘くも辛くもできるものですから、地域環境、お客様のニーズに添うように設置、調整し有効活用すべきものです。
以上のように、経営者の近視眼による目的の取り違えの事例が示すように「産業の方向づけ」がいかに重要かが、お分かりいただけたと思います。
そして、どのようにビジネスそのものを常に革新するかによって、企業の価値が決まってきます。
どんな産業でも栄枯盛衰は必ず生じてきます。そして、成長産業と見ればライバルが出現し、競争が激化してきます。その中でのサバイバルの条件は、この「産業の方向づけ」を明確に掲げ、しかも、お題目ではなく、実行した者が成功することは歴史が証明しています。
この「産業の方向づけ」で共通していることは「情報産業」ということであり、これはとりもなおさず、お客様のニーズに合った活動による「環境適応業」ということです。
今や、ビジネスを起業したり、再構築したり、革新する場合に、絶対欠かせない考え方です。
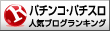 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
