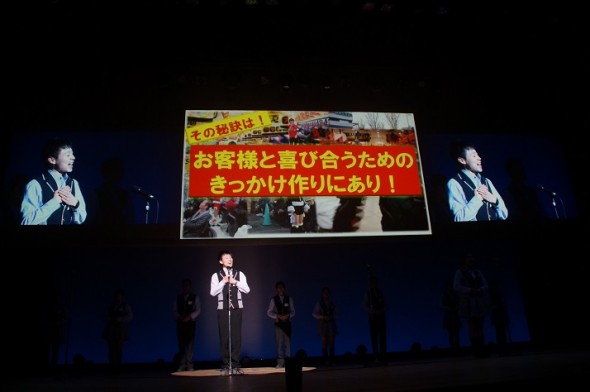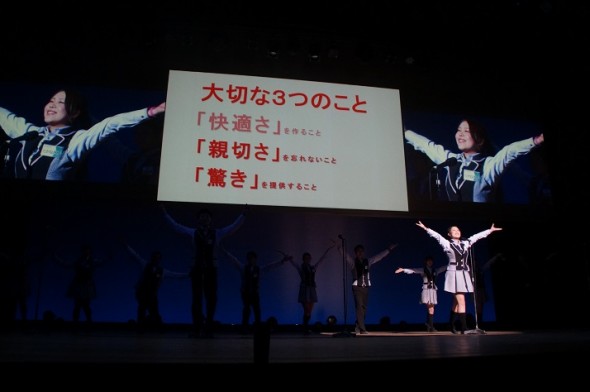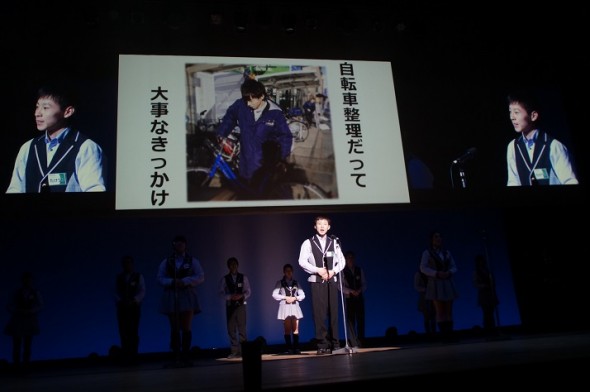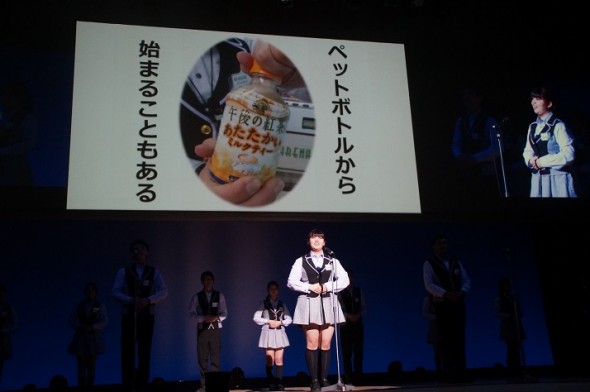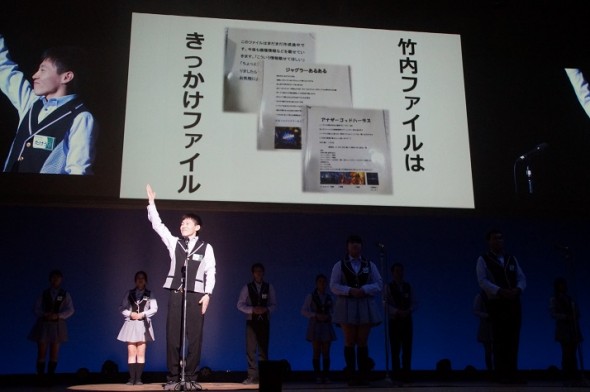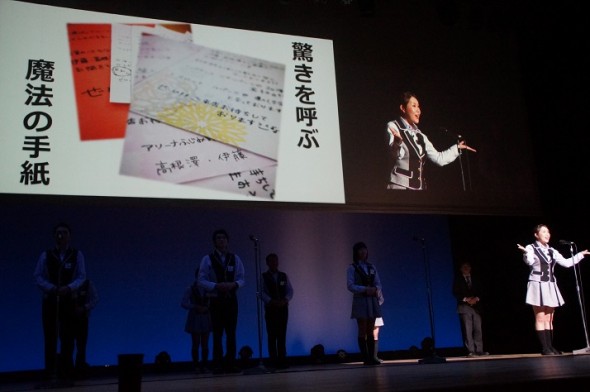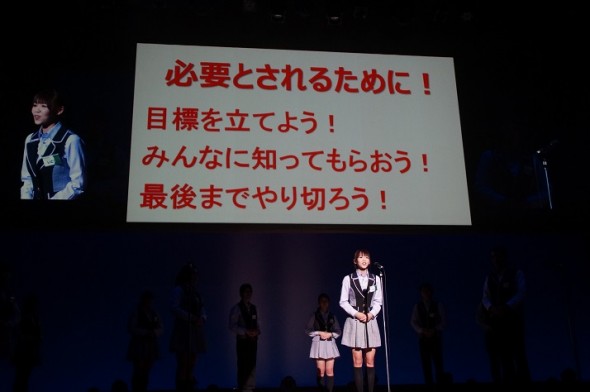要約する。
トヨタがモータリゼーションの元年として昭和41年に発売した初代カローラ。トヨタを代名詞ともなった大衆車だが、その開発過程では、数々の秘話がある。
当初は1000CCで開発していたが、土壇場で変更したのはライバルとして切磋琢磨してきた日産のサニーの存在があった。車名公募に800万通もの応募が寄せられたことから、差別化を図るためにプラス100CCの1100CCでサニーを上回る戦略に出た。
11月発売予定の8カ月前の3月に設計変更が決定した。
たかが100CCのボアアップだが、問題はシリンダーを大きくすれば済む問題ではなかった。トランスミッションの耐久性能などの見直しも行わなければなかった。
この時、それまで主流だったコラムシフトからフロアシフトにチェンジ。併せて、当時はフォードの小型車の一部にしか採用されていなかった軽量・省スペースのサスペンションも導入した。
なにせ、初めてのものを作るのだから、開発陣の苦労には計り知れないものがあった。
この時、開発陣に檄を飛ばしたのが当時は副社長でのちに社長となる豊田英二氏だった。
「エンジンと同じくらい重要な部品だ。外注はまかりならん」と自社開発に拘った。
トヨタが世界的な企業に成長したのは、自社開発の理念があったからこそ、量販型ハイブリット車の販売も世界に先駆けることができた。
一方のパチンコメーカーといえば、液晶という心臓部までを外注に丸投げしているケースが少なくない。これで胸を張ってメーカーといえるのだろうか。
メーカーが苦慮している点といえば、もう1000円、もう1000円とおカネをつぎ込ませる演出だろう。
加えて、値段の付け方も業界特有なところがある。
一般的には製造原価に適正利益を乗せて値段が決まるが、ちょっと違う。
「開発費が丸投げなのでコスト計算が単純。22~23万円で十分ペイできるのに、利益を相当乗せている」
今は40万円ぐらいで足並みを揃える。
パチンコ業界が不思議なことは、新台よりも中古価格が高くなること。ホールも元が取れるとなれば、中古機でも100万円の値段が付くことは昔からあった。
だから、メーカーにすれば、ホールは高くても買う、という概念がこびりついているので、値下げする発想は毛頭ない。
値段は、元が取れれば高くても買うのはいいが、心臓部を外注に丸投げしているようでは、斬新な発想の機械も生まれるわけがない。
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。