ぱちんこ情熱リーグで優勝したベラジオ本店が、日本一のチームを作ることを目的に取り入れた原田メソッドが、結果が出せる教育システムとしてパチンコ業界でも注目されている。

そこで、9月21日、新大阪でパチンコ業界を対象にした「原田メソッドビギナーズセミナー」が開催された。150人あまりの参加者は熱心にメモと取りながら聴講した。

原田教育研究所の代表でもある原田隆史氏が、パチンコ業界の教育に本格的に取り組んだのはベラジオ本店からだった。
ベラジオ本店の特徴は元気朝礼にあった。これを分析した結果、優れているものが1つ、欠陥が2つあった。
朝礼に新しい要素を取り入れ、情熱リーグで日本一になる戦略を日々実践した。その結果、見事に優勝を勝ち取ることができた。
目標達成に必要な要素は次の3つ。
1.テンション
2.モチベーション
3.自信
これを朝礼に取り上げた。
まず、テンションを上げることは比較的簡単にできる。この写真がそうだ。

これはジャンケンをしているシーンで、勝った人は本気で喜び、負けた人は本気で悔しがるように、指示が出ている。これを2回繰り返すだけでテンションは上がる。
しかし、テンションは長くは持続しない。1分で下がる。そこで、長期的にやる気を持続するには、モチベーションが必要になる。モチベーションを持続するには自信が必要になる。
ここで改めて原田氏の経歴を紹介すると、大阪市内の公立中学校で20年間体育教師を務めていた。
赴任した学校は西成区に隣接している土地柄から、荒廃していた。
ピンクの制服を着てくる生徒。
生徒に「おはよう」と声をかけると、
「死ね!」とつばを吐かれた。
学校生活では分からない何か問題を抱えていることが分かった。原因を探るために家庭訪問した。
両親が刑務所に入っていた。怒りの気持ちを何とかしないといけない。
何でこうなったのか?
原田先生は相手の目線に合わせて話を真剣に聞いた。金髪の不良の心を開かせるには話を真剣に聞くことだった。
「家は貧乏や。高校へ行くカネもない。勉強なんかどうでもいい。ほっとけや」
ある生徒は母子家庭で、母親は新聞配達をしながら3人の男の子を育てていた。中学を卒業したら働くしかなかった。
原田先生は生徒にただで高校へ行ける方法を提案した。
「陸上競技で日本一になったら、ただで高校へ行けて、しかも、300万円がもらえる」
「そんなうまい話があるかい。走るのは嫌いや!」
そんな生徒には砲丸投げや円盤投げの投てき種目を勧めた。
「全国大会で優勝したら、ほんまにただで高校へ行けるんやろうな」と生徒たちはだんだん真剣に話を聞くようになった。
「でも、信用できん。紙に書け。判子も押せ」と迫った。
原田先生は紙に書いて判子も押した。
不良たちから公園に呼び出された。学年でもやんちゃな生徒たちが集まっていた。内心穏やかではなかった。
「先生、陸上部に入れてくれ」
「よし、陸上競技で日本一を目指す。ただし、やんちゃで警察の世話にならないこと、後輩の面倒を見ること、老人を助けることを約束してくれ」
その日40人が入部した。1学期が終った時には80人に膨れ上がっていた。
原田先生は荒廃した学校が改善されたケースを求めて、文部科学省に電話した。手本になる中学が奈良と兵庫にあった。
さっそく面会を求めた。
そこで同じことを言われた。
「陸上競技の練習の前に3つのことをやっているか?」
それは再建の3原則で、万国共通のものだった。
1.時を守る
2.場を清める
3.礼を正す
日本一の中学校はいずれもこの3つを実践していた。
1年目は2位だったが、その後7年間で13回日本一になった。
西成育ちの生徒たちは、根性だけは人一倍あった。彼らの頑張りを地域が応援するようになる。
全国大会に出場できるようになるが、家庭が貧しいので遠征費がない。
先生らがカンパしただけではなく、生徒の頑張りを間近で見ていたホームレスがカンパしてくれた。
500円1枚はその日の晩飯代、2枚入れるとその日の宿が本当になくなる。3枚入れると翌日の朝飯も抜きになる。
そんななけなしのおカネを生徒のためにカンパしてくれた。
試合でピンチになると、この500円玉を握り締め、「負けたら帰れない」と砲丸を投げる生徒もいた。
「1日8時間の練習をしても結果が出ない。頑張ることを目標にする生徒は結果がでない。こうなりたい、という目的がなければダメ」
目標は日本一になることだが、目的は「ただで高校へ行って親孝行する」こと。実は日本一になる目標よりも、「親孝行する」目的がより重要になってくる。
ある年の修学旅行で旅館で靴を揃えることを目標にしたことがあった。
前年の修学旅行で旅館からブラックリストに載るほど恐れられていたからだ。
冷蔵庫からビールは盗む、みやげ物はなくなるで、二度と来て欲しくない中学校だった。
そんなこともあったので、靴を揃えることを徹底した。しかし、200人中、199人が揃えても、1人でも揃えなかったらそれは0点だった。
そういう場合、やらない生徒の靴は先生が揃えた。これをハンズオン指導(手を汚す)という。一番手ごわい生徒に、垂範率先して見せた。
靴揃え日本一の中学校を目指すと、生徒の態度も変わっていった。
旅館へ到着して自分たちの靴を揃えたのは当然だが、食事の後片付けも手伝い、食器を炊事場まで運んだ。
炊事場で洗物をしていたのは、腰の曲がったおばあちゃんだった。それを見て生徒の何人かが洗物を手伝った。
それだけではなく、おばあちゃんのマッサージまで始めた。
その姿を見た旅館の主人は、同じ中学の生徒とは思えない変わりぶりに涙を流して感激した。
そして生徒たちに「私もあなたたちのように日本一の旅館を目指す」と誓った。
つづく
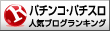 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。


