船井総合研究所のコーポレートフェローの小森勇氏より、1物1価の概念を変える寄稿が寄せられた。この方法を業界が採用すればホール営業がある意味楽になる。
以下本文。
業界で今最も使用頻度の高いキーワードの1つは、間違いなく「1物1価」ではないでしょうか? しかしこの1物1価とは、そもそもどういう意味を内包した言葉なのかについての突っ込んだ考究は、寡聞にして知りません。そこで今回改めて本質的考究を試みるべく筆を執りました。
当局の指摘されるお言葉の中には「2物2価」は問題外である! というのも見られます。ところがこれについても「2物2価」とはどういうことを意味するのか? またどうして2物2価はいけないのか? についての詳しい説明は見られないのではないでしょうか?
そこで、2物2価に触れる前に、1物1価から考究してみる必要性が高いでしょう。
重要な着眼点を振り返りましょう。
当局は1物1価だけを切り離して議論する弊害にも言及されています。すなわち、1.賞品の「市場価値」 2.賞品と玉・コインとの「等価交換」 3.「1物1価」とを、いわば三位一体的に議論しないと本質は見えてこないということです。
まず「市場価値」です。
言い換えるならば、賞品は、一般賞品か特殊賞品かを問わず、その価値と価格との間に“市場性”がなければならない! ということです。
そこで分かり易くするために200円のチョコレートを賞品として考えてみましょう。
中身は全く同じながら、一般商品の方は赤ラベル、特殊賞品の方は黒ラベルとします。
どこのスーパーだろうがコンビニだろうが、200円のチョコレートの仕入れ価格(下代)は8掛けの160円位とします。
仕入れ値と販売価格との間にはマージン(粗利)が生まれるのは資本主義の常識です。
当局のご指摘は、200円の賞品を200円か、200円以下ギリギリで仕入れるのでは通常の商取引ではない! という点です。
結論を先に言うと、3店方式(ないし4店方式)を円滑に機能させていこうとするならば、各店でちゃんと適正なマージンが生まれる仕組みでないと、賞品がほぼマージン無しで還流することになり、つまり賞品は単なる「換金ツール」として循環するものと看做されても文句が言えない!ということなわけです。
200円の黒ラベルチョコレートが特殊賞品だとしても、パチンコホールの仕入れ値が160円だとすると、そこに20%の粗利が生じるわけだから、出玉率(機械割数)は、100%(10割営業)で十分20%の粗利確保ができる! と仰っているわけです。
もっと言えば出玉率調整によって、8.8割営業やら12割営業やらと業界人が言うこと自体がナンセンスということになります。
<賞品仕入れによるマージン確保の努力>という意味と、<等価店だと割数が8割営業などという業界常識を頭から捨て去る!> というこの2項目がどうにも理解できない読者の方は、これから先の文章が理解困難でしょうね。
200円のチョコレートは、ラベルの色が赤(一般)であろうが黒(特殊)であろうが、等しく4円パチンコの場合、50玉交換でなければならない。
一般賞品の時は50玉交換、特殊賞品の黒チョコの場合は60玉交換(3.3円営業)というPOSの読み取りは、1物1価の点からも、また市場価値の点からもおかしいですよ! ということです。
これが当局の仰る「等価交換」の原理です。
従って、<33玉交換、6.6枚交換>だから1物1価をやっているというのもオカシイわけだし、また<25玉、5枚交換だから1物1価だ!>と胸を張れるわけでもないのです。
なぜなら後者は大多数の店が店の外の賞品買取所においても250玉=1000円で交換できますよ、といっているのと同様だからであります。
この際はっきりしておかねばならないことは、当局の仰る「等価交換」の原則というのは、店内の賞品カウンターにおける、顧客の賞品玉(獲得玉)と賞品との「交換」(民法第586条)のことを仰っているのであって、店外の賞品買取所で顧客に渡される“現金”額における、いわゆる「換金等価」のことでは断じてない! ということです。
ところが、驚くべきことに全国の組合理事会で侃々諤々議論されている流れを聞いていると、まるで<4円等価交換、20円等価交換しかない>という誤解がまかり通ったような議論なのです。
このことから真の「1物1価」を成立させようとすると、以下のように成らざるを得ないと考えられます。
すなわち、昨年夏に大阪府警の保安課から指摘があったように、「賞品買取所」の問題にまで踏み込まないことには、絶対に「1物1価」の問題の解決策は見つからないということになります。

まずP店(A)は200円の黒チョコ(特殊賞品)を賞品問屋(D)から160円位で仕入れねば成りません。
仕入れた黒チョコをP店カウンターでは50玉(10枚)の玉・メダルと等価交換します→ ※ここでP店には20%の粗利が生じます。
交換された黒チョコを遊技客は店外の「賞品買取所」(B)へ持っていきますが、問題はその時の買取額です! 私の理論では140円(くらい)で買い取らないと、以下の賞品故買の流れが成り立たなくなります。
「賞品買取所」で買い取られた黒チョコは、その晩か翌日、中堅故買業者(C)によって145円で引き取られます。※「買取所」はここで5円の“適正な”マージンを教授します。
故買業者(C)は買い取った黒チョコの品質チェック(ex.X線検査)をした上で、賞品問屋(D)に150円で持ち込みます。※(C)にもここで5円のマージンが発生しますが、これは運送、検査代を賄う必要利益です。
賞品問屋(D)はこれらの商品を検品のうえ、P店(A)に160円で販売します。
いかがですか?この図式を見て溜め息つかれる方が多いのじゃないでしょうか?
そうです。200円の特殊賞品は140円くらいで買い取られないことには、特殊賞品の3店方式、いや正確には「4店方式」は成り立たないのではないか? ということに気付かされると思うのです。
→ <これじゃ等価じゃねえぞ!>とお怒りの方は、私に言わせて頂くとよっぽと脳血管が詰まっておられる可能性が高いと申せます。
また、<なぁんだ、これじゃ昔の2円50銭と殆ど変わらないじゃないか!>と叫ばれる方に申し上げたい。
<ハイ、その通りです。昔の大先輩たちは難しい1物1価論やら、等価交換原則やらが分からなかったかもしれないけれど、近江商人の哲学とも言える「三方良し」(=お客良し、お店良し、仕入れ問屋良し・社会良し)の考えを経験的な叡智によって実践していたのではないか!>
さてここまで進んだところで、やっと「2物2価」の議論の検討に入れるわけですが、この続きは次回の発信と致しましょう。この3頁だけでも大議論沸騰の可能性大だからです(笑)。
つづく
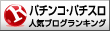 あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
あなたのポチっ♪が業界を変える
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
![]() あなたのポチっ♪が業界を変える
あなたのポチっ♪が業界を変える

