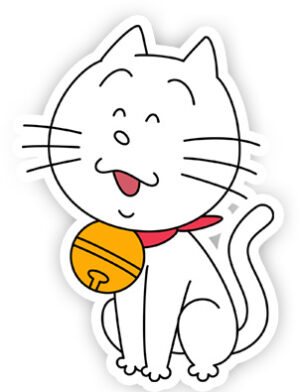この業界関係者の地域の郡部では、3店方式がもはや建前と化している。地域的に経費的に景品問屋が動けない。動けば動くほど赤字になる。ホールは景品問屋に伝票代を支払っているだけ。
景品買取所の人件費もままならないので、ホールの従業員がときたま中に入ったりすることも。これを警察のお目こぼしで何とか続けることが出来ているが、時折、自家買いで摘発されることがある。このお目こぼしがいつまで続くかどうかが不安で仕方ない。
そもそも3店方式の元祖である大阪方式が経営破綻したことでも分かるように、地方の田舎となれば推して知るべし。
「警察にとってパチンコ業界は利権なので潰すことはない…」――そんな思いが業界関係者の頭の片隅にはある。根本的な解決策として願うのが「パチンコ業法」の制定だ。
風営法の下では、パチンコはあくまでも遊技だ。パチンコで遊技の結果に応じて提供される賞品について、「一時の娯楽に供する物」として賭けたにとどまるときは、賭博罪が成立しない。
特殊景品を3店方式という方法での換金が違法でないのは、3店方式が厳密に守られている時だ。
業界が儲かっている時は景品買取所の取り扱い額も多かったので、問題なかった。時代が変わり、売り上げが激減、透明性が求められる中では、この3店方式自体が制度疲労している。
パチンコ業法が成立し、換金が正式に認められれば、この業界は新たな形態で成長できるかもしれない。それは同時に、警察の「利権」も構造的に見直される必要があるということだ。
問題は、業界内でもパチンコ業法に反対する勢力が根強いことだ。 特に、業界の「重鎮」たちは、この新しい整備法が業界の危険だと信じている。それが正しいかどうかは別として、彼らの影響力は大きく、現状を変えて進まない最大の原因となっている。
そんな中で、業界関係者が「重鎮が鬼籍に入るまで待つしかない」と言うのは、素朴な冗談ではなく、ある種の諦めを含んだ現実的な感情だ。
田舎では、未だにパチンコが主要な娯楽として君臨している。映画館もテーマパークもない地方では、ホールの明かりが「町の灯火」として機能しているのだ。業界の存続が地方経済や地域社会にとってやはり重要である。
しかし、その光がこのままの状態で維持できる保証はない。3店方式という危険な綱渡りをいつまでも続けることはできないだろう。
「パチンコ業法」という新たな道を見通しつつ、変わらない現状をただ待っているというジレンマ…。地方社会の消え入りそうな「灯火」を守るために、なんとか制度を変え、透明性を確保しているかにかかっている。
パチンコ業法が実現する日は来るのだろうか?
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。