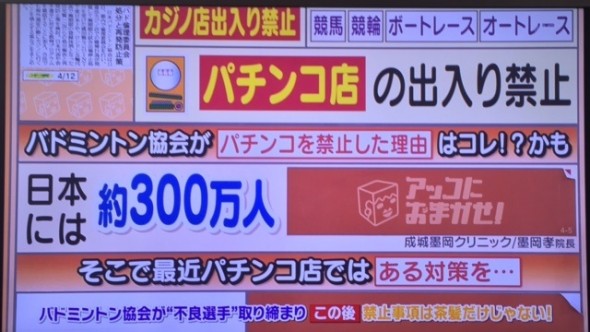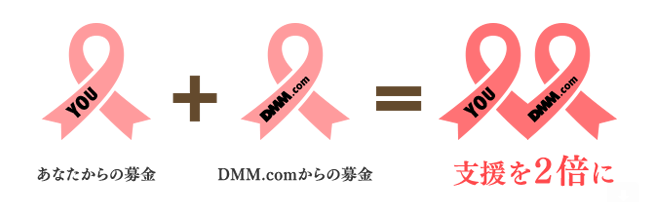「今まで、大手しか相手にしていなかったような営業マンから電話がかかるようになった」(店長)
「新年のあいさつに所長や支店長が来るようになった」(営業部長)
これらの声は中小ホールからのものだ。メーカーも台数が捌けなければ営業マンが必死になるしかない。1台でも多く買ってもらうために営業マンの力量が問われる。歯牙にもかけなかったホールへも営業攻勢をかけるメーカーがある一方で、上位100社の優良ホール企業しか相手にしないメーカーも出てきている。
強気なメーカーにすれば、新台を買ってくれるホールが客であって、中古しか買わないホールはそもそも客ではない、という考え方だろう。
業界が絶好調だった時代、あるメーカーは「注文を断ることが営業マンの仕事」だったこともある。断られないようにホール側は営業マンを接待攻勢漬けにしたり、あるいは営業マンを拉致するという強硬手段を取ったりと、刑事事件になるような機械の争奪戦が展開された。
昔は「買わせてやる」とあからさまな態度の営業マンもいた。また、支店長は「どこでもいいから、兎に角突っ込んで来い」と発破をかけることもあった。
ホールが主導権を握ることで今は「買っていただく」「入れさせていただく」に変わってきた。
どんな商売でも買う側のお客が強いはずなのに、パチンコ業界は長らく売る側が強かった。それはホール側が新台がなければ営業できない、という先入観があったからだ。
それはさておき、販売台数が減少する中で、メーカーが考える売上高の確保は値上げだ。
一番単純な方法だが、少子高齢化の影響で旅客収入が減少する鉄道会社の場合は、どうだ?
少子化で学生定期券の販売も減る。
大都市圏で朝夕ラッシュ時に「毎日、座って通いたい」というサラリーマンの夢を叶えるのが、定期券に追加料金を払えば、座席が確保できる列車だ。
JR東日本は東海道線や横須賀線や総武線快速にグリーン車を連結していたが、2020年をめどに中央快速にグリーン車を2両連結させる。
これに刺激され、特急車両を持つ小田急、西武、京成、東武の4社が通勤時間に特急車両を運行して、追加料金で座れるサービスを展開している。
ホールにもこうした付加価値を付けることで、売り上げをアップする発想が求められる。
これは首都圏で人口が多いから、そういうこともできるが、地方の私鉄では論外である。同様に地方のホールも人口が減少する中で、今後、どうやって収益を確保するかが問題になってくる。
「地方は1パチで収益が上がらなくなったら潰れるところも出てくる。景品だけで遊技人口を増やす発想が必要になって来る」(金融関係者)
景品だけで遊技人口が増やせたらノーベル賞ものだが、新たなジャンルを作るぐらいの気持ちで取り組まないことには、遊技人口はじり貧になることだけは、見えている。
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。