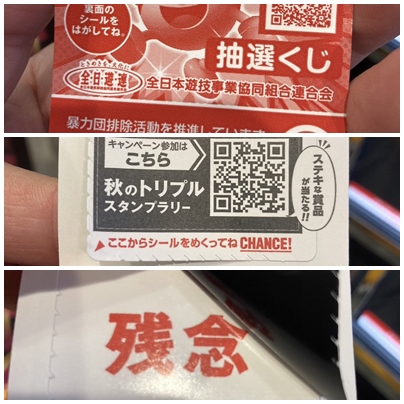食料品、衣料品、日用品、家電製品まで、一箇所で手に入る便利さは圧倒的だった。しかし、少子高齢化とライフスタイルの変化が進むにつれ、そのビジネスモデルは徐々に崩壊していった。
消費者の多様化したニーズに応えきれず、専門店やネット通販に押されていった結果、総合スーパーはかつての輝きを失ったのである。
11月26日付のヤフーニュースにも詳しい。春日部の“シンボル”「クレヨンしんちゃん」の聖地 52年の歴史に幕…イトーヨーカドー相次ぐ閉店の背景は
少子高齢化に伴い、若年層が減少し、家庭を持つ世帯も少なくなっていく中で、総合スーパーの顧客基盤は縮小していった。かつては家族全員で週末に買い物を楽しむ風景が当たり前だったが、今や一人暮らしや共働き世帯が増え、消費行動も変わってきた。
効率を重視する現代人は、日用品をコンビニで手早く購入し、洋服はファストファッション、食料品は専門店で買い求めることが多くなった。
さらに、オンラインショッピングの台頭が総合スーパーにとって大きな脅威となった。Amazonや楽天といったECサイトが、24時間いつでもどこでも購入できる利便性を提供することで、総合スーパーの来店客数は大きく減少した。
消費者は、わざわざ足を運んで店内を歩き回る必要がなくなり、クリック一つで欲しいものを手に入れることができるようになった。
このようにして総合スーパーのビジネスモデルが崩壊していった背景には、顧客のニーズの変化に対応しきれなかったことが挙げられる。総合的にすべてを取り扱うことにこだわり続けた結果、専門性を持った小売業態や、利便性を追求するオンラインショッピングに太刀打ちできなくなったのである。
この総合スーパーの失敗は、パチンコ業界、特に1パチのビジネスモデルに重ね合わせることができる。
1パチは、かつては「手軽に遊べる娯楽」として多くの高齢者を惹きつけてきたが、その顧客層はまさに少子高齢化の影響を受けている。高齢化が進む中で、1パチを支える年金生活者たちは、体力や興味の減退とともにパチンコホールから足を遠ざけている。これは、総合スーパーが顧客の減少とともに崩壊していったのと同じ道を辿っていると言える。
さらに、パチンコ業界は許可産業であり、自己改革の自由が少ないことが、この問題をさらに深刻化している。
総合スーパーが安売りやセールで集客を試みたように、パチンコホールも1パチを主軸とした薄利多売のビジネスモデルを採用しているが、それは一時的な延命措置に過ぎない。
総合スーパーが価格競争に敗れ、結果的に店舗を閉鎖していったように、1パチユーザーが減少し続けることで、ホール企業の経営はさらに厳しさを増すことが予想される。
ホール企業が今後生き残るためには、新たなビジネスモデルの構築が不可欠である。1パチに依存し続けるだけでは、総合スーパーが辿った崩壊の道から逃れることはできない。
スロットに押され、最近の4パチの稼働低下も深刻だ。このままではパチンコ自体がスロットにシェアを奪われ、パチンコそのものの存続が危ぶまれる。
※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。